 ロゴをクリックでトップページへ戻る
ロゴをクリックでトップページへ戻る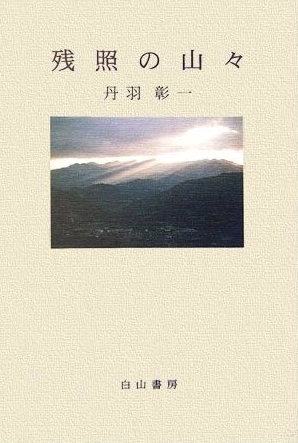
| 『残照の山々』(丹羽彰一著・白山書房) |
| 私の本棚にずらりと並んでいる山岳書をざっと見渡すとある特徴に気づく。背表紙の著者名に文章を書くことで衣食している、いわゆる作家と呼ばれる人がほとんど見当たらないことである。 ママリーは「登山家は遅かれ早かれ執筆症候群の餌食になる」(『アルプス・コーカサス登攀記』海津正彦訳)という言葉を残しているが、実際にその餌食になった人たちが多くの山岳書を残してきたし、好んで読まれもした。 読者がそれだけあったのなら文章を書くプロである作家がもっと山岳小説を生産してもおかしくないはずだがそうはならなかった。それは小説より奇なる事実に満ちた山の実情を知る登山者が架空の話では満足できなかったからだろう。実話では語れないときに小説の出番がある。 山の文章の主流は登山者が自らの体験を書くノンフィクションだった。重要なのは文字通り虚構を排した事実で、しかも人の耳目をひく特異な事実すなわち初登頂や初登攀などの成果が作品の価値の筆頭だった。しかしそういった磨かずとも光る玉を拾うような厳しい登山をできる人は限られていたし、やがて玉も枯渇した。 事実にさほどの価値も見出せなければ、読むに値する文章はおのずと文学的な達成を持たざるをえない。登山が大衆のレジャーになって「執筆症候群」の餌食になる登山者も膨大になったが、ママリーの時代とは執筆の内容が変質したのである。 旅や登山はすべからく趣味であるべきものである。徒労を徒労と思わない遊びであることが多くの記録とその文学を生んだ。しかし地理的な未知の克服に驚喜する時代はとっくに終わった。現代の山の文学はこれまでにも増して風流韻事であることを旨とし、滋味こそを作品の価値としなければなるまい。 私は表題の本の著者と商売上とはいいながらお付き合いがあった。ここでは親しく丹羽さんと呼ばせてもらおう。 この本には先人の文章に触発されての山歩きが何度も描かれる。すぐれた山の文章が蓄積されている現代ではそんな山歩きの妙味がまた新たな文章を生む。そして丹羽さん好みの人影まばらな山であればこそ、丹羽さんのようにひとりで歩けばこそ、その味わいは深まる。 中に「猿橋の小さな山二つ」という文章がある。二つの山とは中央線猿橋駅鳥沢駅間の線路の南側に盛り上がる太田山と天王山、いずれも五五〇メートル程度の低山である。背後にその倍の高さの高畑山や倉岳山といった、中央沿線の人気の山が並ぶとあっては好事家の目にしか留まるまい。もちろん歴とした登山道はない。 私は丹羽さんと山選びの志向が似ているから、こういった山は気になる。同じ山梨県内であっても大月以東の山は信州境に住む私からすると遠い山で少々馴染みが薄い。この二山もまったく知らなかった。そこで丹羽さんが先人の文章に導かれて歩いたひそみにならって、私は丹羽さんの文章をなぞって太田山に登ってみることにしたのである。 「(太田山の頂上に登り着いたがさしたる面白みもなかった)だが、細長い山頂を西南末端までたどっていくと、小さな石仏が落ち葉のなかにひっそりと座っていらっしゃるのを見つけて狂喜した。まことにおだやかなお顔だちで、天保十三年と彫られている」 太田山に登ってみたいと思ったのは右に引いた一文があったからでもあった。暮らしと山が結びついていた時代、山への畏敬から身近な山にも石仏や石祠などが置かれた。今ではまず滅多に人の目に触れることもないそんな石造物に出会うのもこうした山を歩く楽しみのひとつである。太田山の石仏を私も見たいと思った。 平成十年の桜の時季に丹羽さんは登っているから、私が登ったのはその十五年近く後になる。この一月の終わりであった。 鳥沢駅から桂川へと下る。月半ばに降った大雪がまだ日蔭にはかたく凍りついていた。藤崎の春日神社からは牛の背のような山容だと丹羽さんが書く太田山は、桂川にかかる、中央線に平行する橋から見るときれいな三角形をしている。 付近の枝垂桜が見事だったという福泉寺のすぐそばから丹羽さんは尾根に取り付いているが、私は寺の裏手に続く地図上の破線をたどることにする。丹羽さんが大手から山に入ったとすると搦手から入ることになる。 尾根筋を倒木を乗り越えながら進むと太田山と天王山をつなぐ稜線の鞍部の近くに出た。径はここで左右に分かれてそれぞれの山頂へ向かう。左の太田山へは部分的には怪しくなるものの山腹をからんでまずまずの径が通じていた。 ひと登りで頂稜の西南の端に出た。丹羽さんの文章にはこのあたりに石仏があったとあるが見当たらない。風の通り道にでもあたるのかおびただしい倒木が折り重なっていて、その下敷きになっているならとても見つけられない。 とりあえず最高点に行ってみようと枝を分けてゆるく登っていくと、どうもここが頂上らしいと思える場所にちょこんとその石仏はあった。  天保十三年の字が見えるので間違いあるまい。馬頭観音である。誰かが移動させるはずもないので丹羽さんの記憶違いだろう。そそっかしかった丹羽さんを想った。 太田山の頂上で読み返そうと私はザックに『残照の山々』を入れてきていた。倒木に腰かけてページを繰ったあと、石仏の横に本を置いて手を合わせた。 丹羽さんが亡くなったのはこのひと月前だった。『残照の山々』に導かれて私も太田山に登り石仏にまみえたことを存命中に話したら喜んでもらえただろう。しかしそうした考えを思いつくのはいつでも手遅れになってからである。 付記 丹羽さんについては横山厚夫さんの「あの頃の山と人」も読んでほしい。 |