 ロゴをクリックでトップページへ戻る
ロゴをクリックでトップページへ戻る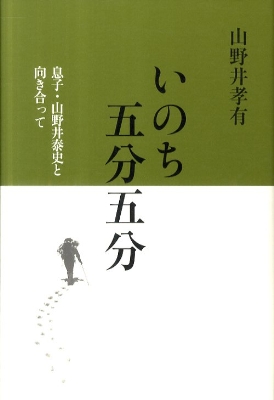
| 『いのち五分五分』山野井孝有著・山と溪谷社 |
| 青春と呼ばれるような一時期は死生観を感傷が支配しがちだから、志半ばで山に果てた登山者たちの冒険譚が若者を山に引きつける理由にもなった。有り余る生気が死を呼び寄せることがある。そうしてさらに多くの若い登山者が死神に誘われて死んだ。しかし我々の今は無数の死屍累々の上にあることを思えば、それを青臭いヒロイズムと嗤うわけにはいかない。 年齢を重ねればかえって人は命が惜しくなる。のるかそるかといった登山をしていた人も山で死ぬことを馬鹿馬鹿しいとある日思えば憑物は落ちる。そしてほとんどの人から憑物は落ちる。生気が薄れた分、死は彼方から漫然とやってくるものになる。登山を続けるにしても捨て身の山からは遠ざかり、めでたく少し健康になるのである。つまり健康であろうとすることは一種の諦念を伴う。 しかし一方、憑物が落ちない人が少数ながらいて次から次へと目標をさらに高く掲げて挑戦を繰り返す。死ぬ危険はますます高まるばかりである。彼らが成果を上げれば世の賞賛を浴びる。これは凡人の成し得なかった業績に対する喝采という意味では、学問的な手柄や観客のいるスポーツの新記録へのそれと似てはいるが非なるもので、物事が奇異であればあるほど耳目を驚かすといったことに属する。自ら望んで命を賭すことほど並みの人間にとって奇異なことはない。だが人間には死に近づいて覗き見たいという欲望がある。そこで他人の冒険や架空の物語の中にスリルを味わって代償とする。したがって冒険はもちろん映画や小説の主人公の多くは命がけである。 人の肉体的な能力の限界がともすれば命を失うような場面で高められていくのは偉大なことだが不健康である。だから少なくとも表面的には健康を尊ぶ新聞社や役所などがそれに賞を与えて顕彰するのには違和感をおぼえる。かつて植村直己に詩誌『歴程』が賞を与えたことがあったがその方がよほど似合う。命の意味を端的に探るという点で孤高の冒険は至高の詩に通じるところがあるからだ。 登山家山野井泰史妙子夫妻の父、山野井孝有氏が書いた表題の本に興味をおぼえて読んでみた。というのも登山家の遭難を登山家自身の悲劇に見立てることが私はかねて不満で、悲劇は危険を承知で送り出したり、結局この世に残されることになった近親者にのみあると思っていたからであった。 世間にはすこぶる理不尽な死がいくらでも転がっていることを思えば、登りたい山に登れずに死んだ無念など物の数ではない。登山家に悲劇があるとすれば、そうまでしなければ生きている実感が得られないような業を背負ってしまったことだとでもいうしかなく、すなわち登山家の悲劇は生きている間にこそある。もっとも登山家自身はそれを幸福に思いこそすれ、少しも不本意には思っていないだろう。それをあたかも悲壮な決意の登山に仕立てて商売にするのがジャーナリズムというもので、そうした方が大衆に喜ばれるからなのは言うまでもない。 著者はまえがきに書く。 〈挑戦者の家族の不安と苦悩は世に出ることはない。これまでも多くの挑戦者がこの世から去った。その挑戦者の家族、特に母親の「不安と心配」は計り知れないものだ。私とかみさんが、泰史に対して、そして妙子が加わってから、お互いが「いのち」とどのように向き合ってきたかをできるだけ正確に記録しておくことは、多くの挑戦者の家族の思いでもあると考えられた〉 しかし著者は子らを失ったわけではない。そして息子夫婦はその世界ではもう功成り名を遂げた人物である。文中にあらわれる息子夫婦の暮らしぶりは俗世の物欲とは無縁で自分たちの目的のためにはひたすら高潔であろうとする。このような人たちにしてはじめて偉業を成し遂げられるのかというような異才の夫婦である。 「親バカとの批判も受ける」と著者が書くのは心配をかけられながらも息子夫婦を誇らしく思う気持ちが我知らず文章ににじみ出たからだろう。多くの人がついに自分が真にしたいことがわからないまま、他人の欲望を自分の欲望だと錯覚するか納得させて暮らしていることを思えば、おのが欲求に忠実に生きられることほどの幸福はないのである。子供の幸せが親の幸せでなくて何だろう。 となると著者が、命ぎりぎりの山に登る息子や娘を持った親の不安や苦悩を書こうとしたのにもかかわらず、読後の印象はむしろ幸福な親の手記とも感じられたのは当然かもしれない。もし子供が山で死んだあとに書かれたものだったらまるで文脈は異なっていたに違いない。死んだ子の歳を数えるようになった親の手記なら幾多の遭難者の追悼集に含まれている。 しかし私はこう書きつつも著者の味わってきた苦汁も同時に思わずにはいられない。『いのち五分五分』という題名は、子が先に死ぬか親が先に死ぬかの割合が、自分が平均寿命に近づいたことで今では五分五分くらいにはなっただろうという意味だという。四半世紀以上にわたって息子が自分より先に死ぬかもしれないという不安にさいなまれてきた著者が、やっと自分が先に逝けるかもしれないと感じたことで初めてこの本を書く心の余裕ができたのかと思うと、それまでの重圧はいかばかりだったかと察せられるのである。 物事にはそうでなければならない順序があって、親が子より先に死ぬことがその代表格である。どんな事情であろうともその逆は不幸と言わねばならない。 今年に入ってすぐ、私は父を見送った。永訣をむろん悲しみはしたが、それにも増して順序が真っ当だったことに安堵した。ただ見送っただけで孝行ぶるのは笑止かもしれぬ。しかしこうしたあたりまえのことが意識の外にあるのが最先鋭の登山家なら、やはりそれは因業というしかなかろう。 |