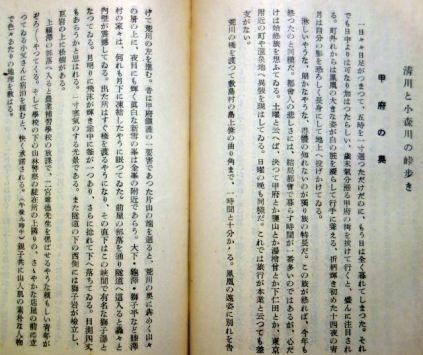
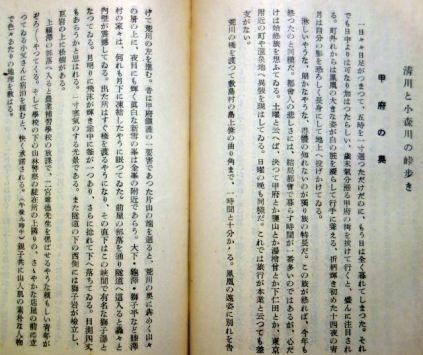
| 清川と小森川の峠歩き |
| 日に日に暮れるのが早くなって5時過ぎにはもう空は暗い。一方、歳末でにぎやかな甲府の街は明るく、異質な登山姿が嫌が上にも目立ってしまう。 街を西に抜け荒川を渡るあたりから上流を望むと、金峰山付近であろうか夜目にも白い新雪の山稜が見える。荒川の支流、亀沢川沿いの道に入ると、点々とある集落の家々はいずれも凍ったように眠っている。 清川村は上福沢の集落に着くとすでに9時半、さすがにもう先には進めない。小さな店先に立っていた男性に宿泊を頼むと快く応じてくれた。その夜はこの家の親子に周辺の地理について教わった。 翌朝、ひと昔前のような安い宿賃に恐縮しつつ出発する。右手に太刀岡山の鋏岩を仰ぎ見てさらに亀沢川上流へと高く登るにつれ、地面は雪に覆われるようになった。金ヶ岳と曲岳の鞍部、観音峠までは雪のせいで時間がかかってしまった。 峠の北側は小森川の源流域で、沢が入り組んで地形の複雑なところである。しばし迷ったりしながら、以前歩いて見覚えのある径に出てほっとした。この山旅の目的は、小森川本流の渓谷を探ることだったが、それにはもう遅いと、径で出逢った、岩ノ下集落に住むという炭焼き帰りの人の家に泊めてもらうことになった。 韮崎から増富温泉へ向かう道は塩川に沿っている。その途中で東から合流するのが小森川で、右岸には延々と岩の絶壁が連なる。岩ノ下とは文字通りその岩壁の下にうずくまるような集落で、先年そこを訪れたとき、上流にあるという奇勝の話にいたく遊志をそそられたことが今回の山旅のきっかけだったのである。 炭焼きの家はかつて辺りを支配した豪族小森将監の末裔だという。その夜の炉端では、今日自分が迷い歩いた谷に繰り広げられた豪族同士の争いの歴史を拝聴した。 翌日は予定どおり小森川の谷を遡った。紺碧の水をたたえた深い淵や次々に現れる飛瀑、聞きしに勝る幽谷の奇観を危うい目に何度も遭いながらも探勝した。源流でやっと安心できる径に出て長窪峠に達する。ここから南に膝まで没する雪に難渋しながら八丁峠へと歩く。峠からは昨日歩いてきた清川村の谷が見下された。もう3時を過ぎていて折悪しく雨が降り出した。 行きがけとは道筋を変えて甲府に戻るつもりで、太刀岡山の北の越道(こいど)という峠を越える。雨脚はいよいよ強い。走るように下り、草鹿沢の集落に着いたときには5時を過ぎ、日はとっぷりと暮れていた。 行き当たりばったりに構えの大きな家の戸を叩いて宿泊を頼むと、家の中には驚くほど大勢の子供がいて、それを理由に断られた。よほどこのまま甲府まで歩いて夜行で帰京しようかと思ったが、真っ暗な中、雨も降りしきるというのではやはり泊るにこしたことはない。路地を下ると灯りが漏れる家があったので戸を叩いたらそこは若い夫婦の家だった。主婦は「部屋が狭いから」と言いにくそうに断ってきたが、自分も若夫婦水入らずの家では気兼ねだったので、これ幸いと引き下がった。 もう甲府まで歩くしかないかと腹をくくったが、少し空腹を満たそうと小さな家で休ませてもらうことにした。 その家では山仕事で大怪我をしたという主人の病床を母子が悲しそうな顔で囲んでいた。そんな状態にもかかわらず、すぐに湯を沸かして茶をいれてくれた。さらには、その濡れようではすぐには乾かない、狭い家で申し訳ないが泊まっていけばよいと言ってくださる。 ちょうどそのとき戸外から声がした。「登山の人が寄ってはいないかい」「ここで休んでいるよ」「ああよかった」 軒下にいたのは最初に宿を頼んだ家の主人だった。傘はさしているが、背に赤ん坊、片手に提灯では、それらを守るために自分はずぶ濡れである。 さっきは断ったけれども、この雨では本当に気の毒だからと捜しに来た。子供が多いのには我慢してぜひ泊まっていってくれという真心あふれる申し出であった。 両方の家からの好意にはほろりとしたり板ばさみになって逡巡もしたが、病人のいる家にはまたの機会を約して迎えに来た主人の家に泊まることにした。 乳飲み子がふたりもいるという忙しい中、この家の奥さんは飯を炊いたり汁を煮たり歓待してくれた。大勢の家族は炬燵と炉端に分かれて団らんしている。自分は両方をかけもって話を聞いたり、また東京の話をしたりした。持参の甘納豆がたいそう喜ばれる。80になるというこの家のお爺さんが語る金峰山の昔話がことに貴重だった。 翌朝は、もう甲府へ出るだけなので出発は遅い。天気は回復し、振り返る草鹿沢はいかにも平和なたたずまいであった。羅漢寺山の尾根筋に通じる御嶽外道は金峰山の里宮金桜神社への参道として栄えたが、荒川沿いの新道が開通して以来寂れ、今では山仕事の人とたまに行きかうだけだった。 こうしてこの年最後の山旅は多くの山水の風景と人情を胸に刻んで終わった。 -------------------------------------------------------- 昭和10年に出版された原全教の『奥秩父・続篇』(朋文堂)は昭和8年の正篇とともにこの山域を知ろうとするときに欠かせない大冊だが、読んでもらいたくともおいそれとは手に入らないのは遺憾である。そこで続篇に収められた紀行の中から一編を人との関わりに重点を置いて意訳してみた。 これを選んだのは、むろん私が読んで感銘を受けたからで、しかし感銘の中身は旧き良き山里の人情云々という単純なものではない。現代人の目で百年近くも前のこういった文章を読むとき、大げさに言えば文明の進歩とは何なのかという命題に突き当たらざるを得なくなる。そしておそらく永遠に、曰く「不可解」なままだろうから思いは複雑になるのである。 |