 ロゴをクリックでトップページへ戻る
ロゴをクリックでトップページへ戻る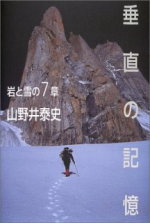
山野井泰史著『垂直の記憶』を考える
新しい本を一刻もはやく読みたいという気が私にはないし、どうせ買うなら古本に限ると思っているから、最近の山岳書では最も話題になった山野井泰史氏の『垂直の記憶』(山と溪谷社)を図書館で借りて読んだのは、出版されてから一年以上たってからだった。 山岳書と一口に言っても、その範囲は明確ではない。それだけ奥行きが深いと言えるし、茫洋としているとも言える。だが、その主流が紀行文学であり、記録文学であることは間違いない。そこで重要なのは事実である。真に語るに足る事実は、ことさらに表現がすぐれていなくとも後世に残る文章たりうることがある。 『垂直の記憶』に満ちているのは、数々の前人未到の単独登攀という語るに足る事実である。それは確かに後世に残りうるものだろうが、かつての、ことに西洋の登山家の書いた、文学と呼ぶのにふさわしい驚くべき精緻さの記録と較べると、どうしても見劣りを感じてしまう。 極度に専門化した分野の登山では新聞社や出版社にとって旨みはないから、文章を書くことを前提に資金援助を受けられたのも過去の話だし、そもそも自由を阻害されることを何より嫌う現代の登山家は、義理を負う立場を避けるだろう。それに、難易度を数字で表わすような現代のスポーツクライミングは、行為そのもので完結し、あらためて文章で表現する必要がない。 山野井泰史という、天才といってもいい異端者の、例えば己の身体の損傷に対しての恬淡ぶりひとつとっても、とても勇気とか向上心で片付けられるものではないが、本人の文章でそれは語れまい。この本以前に山野井氏を描いた、丸山直樹『ソロ』(山と溪谷社)や、以後の沢木耕太郎『凍』(新潮社)のように、いずれまた他の筆者によって書かれることがあるだろう。要するに、最先端のクライマーはもはや他のスポーツ選手のように、書かれる側の人間なのである。 山野井氏にしてみれば、困難な登攀そのものがほとんどすべてで、それを文章にして山岳雑誌に発表していたのは、自分の備忘録としてくらいの気分でしかなかっただろう。 それが、ギャチュン・カン北壁からの命からがらの帰還で、長い入院生活を余儀なくされたときに自伝的な本を書くことになったのは、勝算ありとみて仕掛けた出版社の思惑に、経済的な理由でも山野井氏が乗ったのだろうが、少々皮肉なことに私は感じた。 真にすぐれた才能は自ら主張しなくともおのずと世に出るところがある。かつての登山家たちが、資金や野心のためにメディアを利用したり利用されたりしていた頃ほどの世間への浸透度はなかったにしろ、現代の登山家としては山野井氏はすでに一般的な名声を得ていた。 本を書くきっかけを作ったギャチュン・カン北壁生還劇はかなりマスコミでも喧伝されたし、今まで自身の手による本がなかったことも幸いして『垂直の記憶』はこの手の本としては昨今異例の売れ方をしたようだが、出版社の読みが当たって、前提から売れるべくして売れた本だと思う。内容から火がついたわけではない。 書評は総じて絶賛といってよかった。こういった登攀記をその道の専門家が評すると、どうしても実績にひれ伏すところがあって、文章表現までには言及しない。 しかし、ごく普通の山歩きしかしていない読者が山野井氏の登攀を想像し理解できるものだろうか。おそらくできはしまい。 だが待て。アルプスに近代登山が発生して以来、おびただしい登山が文章になった。今や古典となっている本や登攀記はいずれも当時前人未到の登山を描いたものである。 それらの文章が世に出たとき、読者はその登山を理解できたのだろうか。それだって多くの読者にとっては理解ではなく、錯覚だったのではないか。 書く側の、表現を凝らしてどうにかしてこの光景を伝えてやろうという文章の力と、読む側の今や遅しとわくわくしながら冒険譚を待つ願望が幸福な錯覚を生んだのである。互いに持つ未知の沃野へのあこがれで夢を見合ったのである。 モンブラン、マッターホルン、アンナプルナ、エベレスト、マナスル、そして、未踏だからこそ大衆に知られた山々。なんと具体的で魅力的な名前だったことだろう。 そういった大物が次々と陥落していった結果、共有の夢がなくなった。いかに未踏峰であろうが、無名峰はついに無名峰で終わったのである。書き手と読み手の興味が細分化して容易には一致しなくなったのである。登攀が困難であればあるほど、それに応じた筆力が必要だが、それも退化していった。 本を書いたのち、山野井氏は雑誌のインタビューに「10人、20人が読んでわかってくれればそれで充分」と答えているが、少なくとも、書き手と読み手が互いに文章で共通の未知の夢を見合った時代にはこういった言葉は出てこなかった。 『垂直の記憶』を読む前、私はあるところにこう書いた。 「山の文章に果たして未来はあるのだろうか。傑出した才能が人間の肉体的な限界を押し上げる意味での登山成果に現れることはあっても、おのずとそれは専門化し、ごく狭い範囲の人が理解できる符号のような記録が残されるのみで、成熟した文章として残ることはますます稀になるだろう」 私の書いたことがまんざら見当はずれでもないと、この本を読んであらためて思った。 |