 ロゴをクリックでトップページへ戻る
ロゴをクリックでトップページへ戻る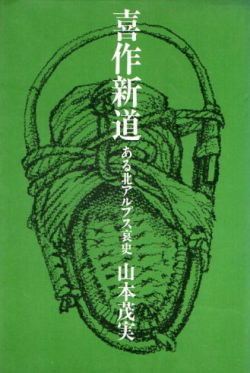
| 『喜作新道』(朝日新聞社)山本茂実 著 ベストセラーとなった『あゝ野麦峠』(昭和四三年・朝日新聞社)の次作がその三年後に出版された表題の本で、いずれにおいても実に執念深い取材で得た膨大な聞き書きや資料から全体を構築する著者の力量には感服するほかない。 著者は前作で、対立する証言があれば双方を示して比較検討し、より真相に迫ろうとする手法をとっているが、それは次作においてさらに際立っている。というのも、主人公小林喜作についての毀誉褒貶が、これが同じ人物に対する評だろうかと思われるほど人によってまるで正反対だからである。 小林喜作は南安曇郡西穂高村牧(今の安曇野市穂高牧)の人で、明治から大正にかけて北アルプス南部ではまず右に出る者のない猟師としてならしていた。 現在、北アルプスでも屈指の人気がある燕岳から槍ヶ岳へのコースは、それゆえアルプス銀座とも称されるわけだが、これが大正時代に喜作が拓いた道で、後に本の題名どおり喜作新道と呼ばれるようになった。 喜作ほか数人の手練れの猟師しか入れなかった、大天井岳から西岳を経て槍ヶ岳東鎌尾根に至る険しい稜線に誰もが歩ける道を開削したのである。これで当時槍ヶ岳登山の表口だった有明から槍ヶ岳への所要時間が半分以下に短縮されたが、この開削はとりもなおさず、喜作が建設を企てていた槍ヶ岳殺生小屋へと登山者を導き入れんがためだった。 その頃喜作は四十代後半、猟の収入もさることながら、槍穂高周辺を誰よりも知る案内人として他の案内人の数倍の料金をとり、蔵が米俵で埋まるほどになっていた。 もともと猟師は貧しい村の中でもさらに貧しい、耕す土地も炭を焼く山も持たない、つまり厳しい山に入って狩猟をすることしか生きる術がなかった者たちだった。それが才覚を発揮して村有数の金満家にのし上がったのだから村人としては面白くない。そんな妬みが「がめつい守銭奴の喜作」という定評をつくった。しかしそれにも一方には金払いがよくさっぱりした性格だったという正反対の証言もあったのである。 だがこれだけでは喜作が伝説化することもなかった。新道が大正九年に開通、殺生小屋が完成して営業を開始、早くも盛況となったのが十一年、さあ順風満帆という翌十二年の二月、これを最後に猟から足を洗うつもりで喜作は黒部谷に入る。ところがひと月近く山中を行動した三月五日(詳細を書く余裕がないが、この地の冬を知る者には驚異的な行動であろう)、宿泊した棒小屋沢の狩小屋が雪崩で押し潰され、睡眠中だった喜作は同行していた長男ともども圧死する。 このとき小屋には喜作父子以外に五人の猟師がいた。それはひとりを除いて北安曇郡平村(現在の大町市平)の猟師で、その五人がことごとくほぼ無傷で生き残ったのだからここに喜作謀殺説が生まれた。 つまり黒部は越中の領分とはいえ、縄張りとしては平村、北の衆のもので、そこに南の衆の喜作たちが入って猟をしたから恨まれ、さらには獲物の取り分を巡って争い、殺されたのではないかというのである。 生還した猟師や北の衆にはむろんそんな説に与する者はいない。一方、北の衆に遅れて救出に向かった喜作の地元南の衆は現場の様子を見て、誰もが喜作謀殺説を裏付ける証言をする。 著者はこれらありとあらゆる相反する証言や文献を検討し、著者自身の推理を加え、最終的には喜作は事故死だったという結論に達するのだが、このあたりはよくできた推理小説さながらである。 それにしても、これは著者も「隣の壁が崩れかかっているのを眺めながら晩酌するのを何よりの幸福とする村人たち」と指摘していることだが、生前には陰口をきいていた牧の村人が死後はいっせいに喜作を擁護する立場に変わったのは、羽振りの良かった喜作に対する妬みがその本人の不幸で一気に吹き飛び、すっきりと暗雲が取れたような気分になったからではなかっただろうか。要するに他人の幸不幸が民衆のエネルギー源なのである。 著者は上条嘉門次亡き後上高地の主と言われた猟師の常さこと内野常次郎を喜作と対比させて書く。無欲の「常さ」に対してがめつい「喜作さ」というわけだが、こんな伝説が、遊びとしての登山が隆盛となって山に入ってきた都会の学生などの評判からも生じていたことに注目せねばなるまい。 つまり彼らにとって、山人とは常さのような、酒さえ与えておけばあとはまるで無欲な人でなければならず、能力に対するしごく正当な金銭の要求でも、山人の喜作がそれをすればたちまちがめつい人間となってしまう。こんな、田舎の人間が純朴だと錯覚する例は今でも都会人に普通にみられる。そしてその逆も。結局、人は自分が理解したいようにしか物事を理解できない存在なのであろう。 その意味からだと思われるが、これだけ膨大かつ綿密な取材に基づくこの作品ですら、ノンフィクションと称するフィクションかもしれない、自分の描いた喜作もまた虚像かもしれないと著者はあとがきに書いている。 山の紀行文も一種のノンフィクションという建前だが、「ノン」を文字通りに信じるなら思慮が浅いように思う。この本に学習院と早稲田の北鎌尾根での先陣争いの逸話が出てくるが、学校が違えばもちろん、同じ仲間ですら発言が異なる。すなわち真実は常に藪の中にある。 「言語には自然とウソをついてしまう性質がある。ひとつの誠を言うために私は八百のウソをつくしかない」と井上ひさし氏が書いているのを読んで膝を打ったことがある。真実など永遠に幻だが、たとえ徒労でも追求する価値のあるもので、そして文章は巧妙な嘘を駆使すること以外、それに迫る方法はないと思うのである。 |