 ロゴをクリックでトップページへ戻る
ロゴをクリックでトップページへ戻る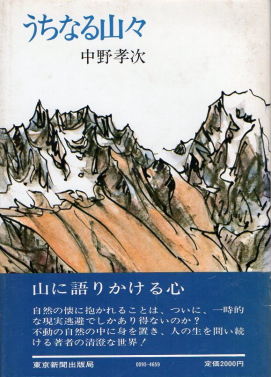
| 『うちなる山々』(東京新聞出版局)中野孝次 著 文章を書くことくらいは誰にでもできるが、それが文学に昇華するには何がしかの気品を必要とする。しかしひとくちに文学といってもとりとめのないところがある。そこでかいつまんだ回答を例えば広辞苑に求めるなら<想像の力を借り、言語によって外界および内界を表現する芸術作品。すなわち詩歌・小説・物語・戯曲・評論・随筆など>とある。 広辞苑が挙げる中でも我が国の近代文学の本流をなしてきたのは小説だった。これには明治時代の言文一致運動の過程で小説家の果たした役割が大きかったことや、かつては小説が娯楽の王者だったことが要因としてあるだろう。読者の欲望を満たすために多くの小説が書かれ、その中には文学の名に値するものも生まれた。 文学の定義だけでも厄介なのに、それをまたジャンル分けするのは難しいし無意味な気もするが、山岳文学という分野は認知されているように思う。そこでは登山者自身による紀行文が大多数を占めるのが特徴だが、一方、本来文学の主流たる、小説家による小説の形での成果をほとんど見ないのも特異なことであろう。 かつて私は、山岳小説が山岳文学の中心になりえないのは、実際の山に小説より奇な事実、ことに劇的な死がそこら中に転がっているからだと書いたことがあるが、これは小説をエンターテインメントの要素に偏って見ている論で、その傾向が確かにあったとしても、いささか皮相だというそしりはまぬがれないように思われる。 そう思うのも、表題の本(1979年刊)の中で著者の中野氏が山岳小説というものが概してつまらない理由を書いているのを読んでなるほどと得心したからであった。 <小説というものは、最も公約数になりえない人間の内的経験を表現するジャンルである。これは言葉で表現できる。しかし山の魅力にしろ、山に憑かれた男の話にしろ、山自体の持つ神秘な魅力を語らなければ何を書いたことにもならない。ところがそれはウィンパーでもジャヴェルでもが経験したように、本来伝達不能な事柄なのである。言葉はどんなにその魅力を客観的に表現してみせても、結局そこに黙って存在する山自身の似せ絵にしかなりえない> ここで中野氏の書く、ウィンパーでもジャヴェルでも経験したこととは、二人ともが山の美や壮観を言葉で他人に伝達できないことへの絶望を書き残していることを指す。 となると山を文章で表現しようとして呻吟し、ついにそれを果たせないもどかしさをうまく書けたなら、それこそが逆説的に山を描いたことだと言えなくもない。 つまり中野氏が言うのは、小説家がいかに山を書いたにしろ、そもそも小説は人間を描くもので山は舞台装置にすぎず、登山家が書く、山そのものの一瞬の美を他人に伝えようとして伝えられない嘆き以上の表現はできないということだろうか。ならば文筆を生業とはしていない登山家が書いた文章でも、少なくとも山で同様の体験を持つ者には、なまじの小説家が書く物よりは心に響くだろうことは想像できる。 だが文筆で衣食するような文学者の書いたものがこと小説に限らず山岳文学の中にそうそうは見当たらないのには別の理由もありそうに思う。 中野氏は自分の出会った文学仲間には山に登らずにいられる人間と登らずにはいられない人間の二種類がいたと書く。 <両者の違いは、片方が、言葉なり音なりによって創造された世界、それを文化といっていいが、この文化を実人生以上に価値ある人間の営みと信じうるのにたいし、片方は、その前にまず自分が生身の人間生物にすぎない事実をことごとに確かめられずにいられない、という点にあったと思う。別の言い方をすれば、前者が、社会的役割としての文学者という立場にたって、専門的文人として生きていこうというのにたいし、後者はその前にまず自分がただの人間であることをなんどでもそのつど確認せずにいられず、実人生を生きるただの人間の立場から文学をみようとした点にあった> 中野氏はむろん後者に属するわけだが、この両者の多寡については言及していない。だがおよそ文学者であれば言葉の信徒で、前者のような書斎派が大勢を占めていたのではなかっただろうか。 人間の内に潜む、山や人跡未踏の極地に出かけずにはいられないような衝動を中野氏は「デーモン」という言葉で表している。この「デーモン」の強弱は人それぞれだろうが、文学者と呼ばれるような人間にはそれが案外希薄か「デーモン」の種類が違うのかもしれぬ。そうでなければ文学者による山岳文学をあまり見ない理由がないのである。 要するに山岳文学とは、山(象徴的な意味で)に登る人が書いて、山に登る人が読む、それ以外にはほとんど無縁な、世にあまねく普遍的とは言えない閉ざされた世界の文学なのだろう。その特殊性にもかかわらずジャンル分けができるくらいの隆盛を見たのは、山に登らずにいられないような人間がこの世には多く、彼らが書くにしろ読むにしろことのほか文章表現と親和性があったからだと思われる。しかしそんな、山と文学が手に手を取って親密だった時代はすでに過去だとも思う。 『うちなる山々』は七十年代後半の『岳人』誌の連載をまとめたもので、数少ない、文学者による山岳書の白眉である。その知識の広範、洞察の鋭利、叙述の巧はやはり登山家というだけではない文学者の力業である。これほどの文章が山岳誌の誌面を飾っていたことに驚かされるのは、現在の山岳誌と較べてしまうからだが、しかし表現する方法の進歩や革新が、ひいてはその目的や結果までをも変質させるのは当然のことで、雑誌の誌面がそれを反映しているなら、今はそういう時代だと言うしかない。山と文学の蜜月は私の中では昔話のひとつである。 |
| 補遺 この本は1997年に小沢書店から同じ内容のまま『山に遊ぶ心』と書名を変えて出版されている。再出版する価値のある内容もさることながら、その間に『清貧の思想』などのベストセラーを書いた著者が高名になったことから、出版社が商機ありとみたこともあっただろう。 中身は同じだから読みたい人はどちらを選んでもかまわないわけだが、書名については前の方が数段すぐれていると私は思う。 |