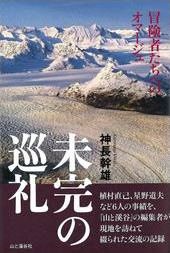
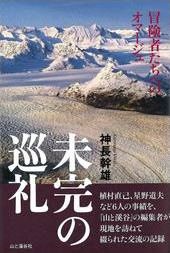
| 『未完の巡礼』(山と溪谷社) 神長幹雄 著 |
| 懐かしや。目次に並んだ名前に新本でお目にかかるのはいつ以来だろうか。植村直己、長谷川恒男、星野道夫、山田昇、河野兵市、小西政継の六氏のことである。 『山の本』の読者層なら説明の要はよもやあるまいが、それでも念のため、登山などの冒険活動で大きな業績を残し、いずれもが山や辺地での行動中に命を落とした人たちであると注釈を加えたほうが親切かもしれない。何となれば、彼らの中では最近の河野の遭難ですらすでに17年前、もっとも古い、植村がマッキンリーで消息を絶ったのが34年前ときては、若い人ならまるで知らない名前でも不思議はないのである。 私としては時の流れの無情を嘆くことになった。というのも、ただ馬齢を重ね、彼らが死んだ年齢よりとっくに上になってしまった自分に内心忸怩としたからである。しかし一方、志半ばで遭難死した冒険者たちを描くという、ともすれば重苦しい内容にもかかわらず、時の流れのこれは功徳であろうか、著者の筆致はことさらに悲哀を強調しない淡々としたもので、読後感はごくさっぱりしたものだった。それには30年以上にもわたって書き留めてきたという文章がやっと本の形になったという、著者の安堵や達成感も作用していると思った。 著者は山と溪谷社で長く編集者をしている人だから遭難の話題など珍しくもなかっただろう。毎号のように「華々しく」死亡記事が載ることなど他の分野の雑誌にはない異常な事態だが、これこそが山岳雑誌の際立った特徴とはいえる。 遭難は珍しくなくとも、最前線で活躍していたり実績を積んで名の知られた者のそれであれば格別の思いを持つはずで、これは編集者だろうが読者だろうが変わるまい。だが我々読者が知りうる情報量が編集者以上であるはずもなく、冒険者たちにじかに接することのできた立場ならではのエピソードも多々あって、そんな、既存の評伝にはなかった初耳の部分も興味深く読んだ。 小西は57、山田は39、そして残りの4人は奇しくも43歳で死んでいる。現代の感覚からいえば小西でも早世だし、それ以外は言わずもがなである。 前にも書いたことがあるが、夭折した者が後世に語り継がれるのは、同時代人がふんだんに生き残っていることによる。若いうちに功成り名を遂げることの多い冒険者の夭折、しかもそれが劇的ならなおさら、死ななかった、もしくは死ねなかった人たちが故人と自分の無念をないまぜにして語り、さらには書き残してくれ、その結果、生前より有名になることすらある。この本に登場する何人かが、冒険は生きて帰ってこなければ意味はないと述べており、むろんそれが本心だとしても、彼らの名前が歴史になお刻み付けられたのは遭難という死に様があったからなのは皮肉な見方だが間違いない。 著者は信州大学や山の出版社を選ぶくらいだから、自身が山や旅への憧れがあった。自分がなしえなかった旅を完成させたか、もしくは途上で果てた彼ら冒険者たちへの畏敬と共感が原動力になって、その痕跡を探す巡礼が始まった。 冒険者たちの家族に会い、生地に赴き、活動した山や辺地をなぞり、最期を遂げた場所へと行脚する。なるほどこの手間では本の完成までに時間がかかったわけである。冒険者たちへの鎮魂は、執念深い、またとない適者にされたものだと思う。 さて実のところ、私は6人のうち星野と河野に関してはさほど特別な印象を持っていたわけではなく、むしろこの本によって彼らの成果や人となりを知ったくらいだった。山田の印象がそれに次ぎ、あとの3人では長谷川、小西、植村の順で印象が濃くなる。 とりもなおさずこの順序は自分の知識の量に比例しており、多少の前後はあれ、この逆順に冒険が表舞台から遠ざかっていったのを示してはいまいか。 植村の著作は70年代半ばの高校生時代には読んでいたし、その冒険はことごとく新聞テレビで知らされた。行方不明になったときのマスコミの大騒ぎはよく覚えている。小西の著作も同じ頃には読み、その後も同時代的に読んでいたのは続々と本が出版されていたからだった。長谷川のアルプス三大北壁冬季単独初登の頃、私は大学生で、その記録映画を山仲間と観た。その意味でもスターだった。 植村についての知識が私に最も豊富なのは、多くが彼の冒険に関心を持ち、一喜一憂し、出版や報道の需要と供給があったからである。それが今ではどうだろう。冒険への関心そのものが薄いうえに、報道されるのは失敗して暴挙だ傍迷惑だと糾弾されるときだけではないのか。 冒険の衰退は地球上の地理的未知の枯渇によるのはもちろんだが、それだけではなく、技術の発達による情報過多が人から表現する力を奪っていることを著者は指摘している。かてて加えれば、インターネットの普及で、過多どころではない量の情報を個々人が送受信できるようになり、自分を棚に上げた人の粗探しを容易にし、極端な清潔主義や安全至上主義をもたらした。安全な冒険などジョークである。自己責任という浅薄な言葉が蔓延し、明日は我が身かもしれない失敗を容赦なくなじり、マナーを守れを錦の御旗に他人の行動を監視する。この清潔主義は狭量で尊大というほかない。相身互いは過去の言葉となった。 「冒険者たちへのオマージュ」という副題を持つこの本は、同時に「冒険へのレクイエム」でもある。植村夫人に、また著者に「(植村または冒険者たちは)いい時代を生きた」という表現があった。二度とないとわかっていての愛惜だろう。冒険への鎮魂曲もまた適者によって歌われたのである。 |